テンプレ流用で他社と同じサイトに…
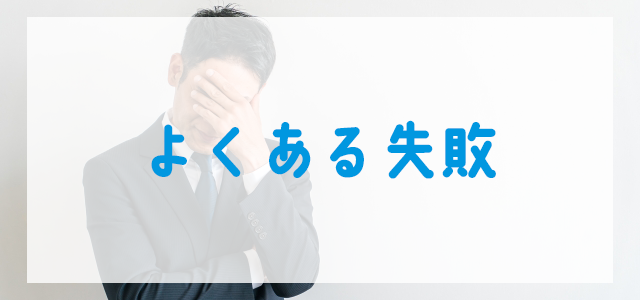
はじめに:「あれ、このサイト見たことある…」
Web制作の現場でよく聞かれる声のひとつが、「他社と似たようなサイトになってしまった」というもの。
とくにテンプレートをベースにした構築や、パッケージ型ホームページの場合、デザインや構成が“どこかで見たようなもの”になりがちです。
この記事では、テンプレートの流用が生む弊害とその背景、さらに差別化・独自性を取り戻すための具体策を解説します。
テンプレート流用の落とし穴とは?
どこかで見た構成、どこかで見たデザイン
「TOP → サービス紹介 → 会社案内 → よくある質問 → お問い合わせ」という構成は、もはや定番ですが、そのまま使えばどこも同じ見え方になります。
とくに同業他社が同じ制作会社に依頼していた場合、サイト同士が“兄弟サイト”のようになってしまうのです。
Googleにもユーザーにも伝わらない
デザインが似ているだけでなく、テキストもテンプレートからの流用だと、検索エンジンからの評価も分散しやすくなります。
「独自性のない情報」とみなされれば、検索順位も上がらず、ユーザーの記憶にも残らないページになってしまいます。
「安っぽさ」「本気じゃない感」が出てしまう
パッと見ただけで「テンプレ感」が伝わってしまうと、その会社の商品やサービスも“没個性”に映るおそれがあります。
特に採用やBtoB営業など、信頼が重要な局面では致命的な印象ダウンとなりかねません。
なぜテンプレートをそのまま使ってしまうのか?
コストと時間の削減が目的
テンプレートを使えば、短期間かつ低予算でホームページが完成します。
制作会社側も提案がしやすく、発注側も「サンプル通りなら安心」と考えるため、導入のハードルは低くなります。
「よくある構成」への安心感
他社サイトと似たレイアウトにしておけば、大きな失敗はなさそう──そうした安心感から、無難な選択に流れてしまうことも多くあります。
しかしその結果、差別化はどんどん失われていきます。
社内にコンテンツを作る余裕がない
文章や写真をゼロから用意するのが難しく、制作会社のひな形に頼らざるを得ないという現実的な課題もあります。
そのままテンプレートに合わせて流し込んだだけ、というケースも多く見られます。
テンプレート流用で起きた“残念な事例”
事例①:検索結果で他社と並んで混同される
あるリフォーム会社のWebサイトが検索上位に表示されたが、競合のサイトと構成もデザインもほぼ同じだったため、
「どっちに問い合わせたか分からなかった」というユーザーの声も。結果的に競合に送信されていたという悲劇もありました。
事例②:採用ページが他社のコピーとバレて炎上
テンプレートの採用ページに文章をそのまま流用していた企業が、競合とほぼ同じ内容のまま公開してしまい、SNSで「パクリでは?」と拡散されてしまいました。
ブランドイメージにも大きな傷が残る結果となりました。
「差別化されたWebサイト」に必要な3つの視点
①誰に届けるかを具体的に定義する
「20代の女性向け」「地元の中小企業」「建設業界の現場監督」など、具体的なターゲット像を明確にすることで、文章もデザインも自然に変わります。
②“らしさ”を表す写真・言葉を用意する
社内の風景・社員の写真・代表者の言葉など、テンプレでは用意できない“自社ならでは”の要素をページに盛り込むことで、他社と明確に差がつきます。
③「お客様の声」や「事例」を積極的に載せる
実際の声や導入実績は、テンプレートでは代替できない最大のオリジナル要素です。時系列で増やしていけば、他社と被ることはありません。
テンプレートから“脱却”するための実践ステップ
Step1:テンプレートは「構造」として使う
テンプレートそのものを否定する必要はありません。重要なのは、「構造の参考」として活用し、中身をすべて独自にすることです。
Step2:テキストは必ず自社で見直す
提供されたテンプレート文章をそのまま掲載するのではなく、自社のサービス・事例に合った表現へ書き換えることが必要です。
Step3:社内素材(写真・声)を用意する
最低限、社内の写真や実績、関係者のコメントは用意しましょう。
これだけでも“借り物のサイト”感はかなり払拭されます。
Step4:デザインカスタマイズを依頼する
テンプレートベースでも、色やレイアウトを変えるだけで印象は大きく変わります。
コストを抑えつつ「うちっぽさ」を出すポイントです。
「安く作る」より「選ばれる」ことが目的
テンプレート流用は、たしかに安価で早く仕上がる手段です。
しかし、Webサイトの目的は“作ること”ではなく、“反応を得ること”です。
問い合わせ、採用応募、資料請求──そのすべては、「この会社にお願いしたい」と思ってもらえたときに生まれます。
コストを抑えつつも、「自社ならでは」を織り込んだ設計こそが、本当に効果を生むサイトの鍵なのです。
