自作したけどスマホで崩れて見えない!
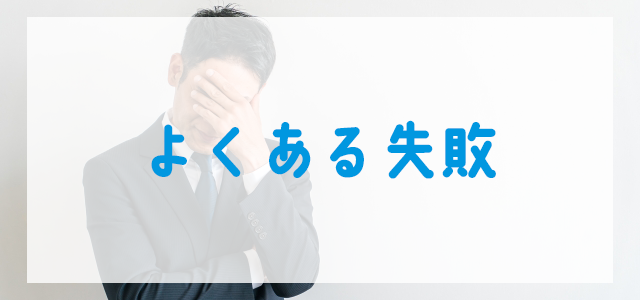
はじめに:スマホ表示を軽視したツケ
「自分でホームページを作ったけど、スマホで見たらレイアウトがグチャグチャだった」──こうした声は少なくありません。特にノーコードツールやテンプレートを使ってPC画面中心に作った場合、スマートフォンでの最適化が大きく抜け落ちてしまうことがあります。
総務省の調査によれば、2023年時点でインターネット利用者の約70%以上がスマホからアクセスしているとされており、モバイル対応は「必須条件」です。
本記事では、自作ホームページがスマホで崩れる主な原因とそのリスク、そして改善のための実践的な方法まで、具体的に解説していきます。
スマホで「崩れる」主な原因とは?
1. PC前提でしか設計されていない
多くの無料ツールやテンプレートは、初期状態ではPC表示に最適化されています。スマホで見たときの段組み崩れや文字サイズの不適合は、そのまま放置されがちです。
2. レスポンシブ設定を理解していない
「レスポンシブデザイン」とは、画面サイズに応じて自動でレイアウトを調整する仕組みですが、自作の場合この設定が正しくされていないケースが目立ちます。
3. 表・画像・文字が固定幅で設計されている
表の横幅が画面より広い、画像が画面外にはみ出す、テキストの改行位置が不自然など、「ピクセル固定」の設計が原因でスマホ対応できないことがあります。
スマホで崩れたときの「見られ方」とは?
1. 一瞬で離脱される
ページを開いた瞬間、レイアウトが崩れていればユーザーは「まともなサイトではない」と判断して、わずか数秒で離脱します。CV率(コンバージョン率)は激減します。
2. 企業や店舗の信用が下がる
スマホでの閲覧時に見づらい、崩れている、押しにくい──こうした印象は、そのまま「仕事の質」や「信頼性」への疑念に変わります。
3. Google検索でも評価が下がる
Googleは「モバイルファーストインデックス」を採用しており、スマホで最適に表示されないページは、検索順位で不利になります。
実例:自作でスマホ崩れ→改善したケース
A社:自作LPが原因でCVゼロ
PCではキレイに見えていたものの、スマホで見ると文字が小さく、ボタンが押しにくいレイアウト。改善後、CV率が0.3%→1.4%に改善した事例があります。
B店:画像スライダーが横に流れていた
WordPressで制作した飲食店サイトで、スマホ画面で画像が右にはみ出してスクロール不能。CSS修正と画像の最適化により、「見づらい」の問い合わせがゼロになりました。
C個人事業主:サービス案内が読みづらい
段落ごとに改行がバラバラで、行間が詰まりすぎていた。Googleフォームもスマホで見切れてしまい、申込数がほぼゼロ→月5件の安定申込へと改善。
自作でもできる「スマホ対応」の対策法
1. ブロック単位でレイアウトを調整する
ノーコードツールやWordPressブロックエディタでは、各ブロックに「モバイル表示」設定があることが多く、ここで余白・位置・フォントサイズを個別調整します。
2. 「実機」での確認を必ず行う
プレビューだけで満足せず、実際のスマートフォンで見て操作してみることが重要です。サイズによって挙動が変わるため、iPhoneとAndroidなど複数端末で確認しましょう。
3. 表や画像は「幅100%」指定が基本
固定サイズ(例:800pxなど)を指定せず、CSSやエディタの設定で「幅:100%」にすることで、画面幅にフィットした表示が実現できます。
スマホ対応を見落とすと“無意味な制作”に
自分で頑張ったのに、誰も見ていない
時間をかけて作ったにも関わらず、スマホで崩れていては誰にも読まれません。努力と成果がまったく結びつかない典型例です。
「スマホは見れればいい」では済まない時代
もはやスマホ対応は特別な設定ではなく、「最低限の前提」です。これを外すと、制作コストそのものがムダになると考えてもよいでしょう。
プロに任せるべき領域もある
全てを自作で対応するのは限界があります。特にモバイル表示最適化は、CSS・レスポンシブ設計の知識が必要な分野です。迷ったら専門家の力を借りる判断も必要です。
まとめ:モバイル対応は“必須条件”である
スマホで崩れるホームページは、「誰にも読まれない・信頼されない・成果が出ない」という3重苦を抱えることになります。
せっかくの自作サイトも、モバイルファーストで設計されていなければ無価値です。
制作前も、制作後も、常にスマホユーザーの目線でチェックする習慣を持つことが、これからのWeb運用において極めて重要です。
