格安制作で著作権トラブルに巻き込まれた!
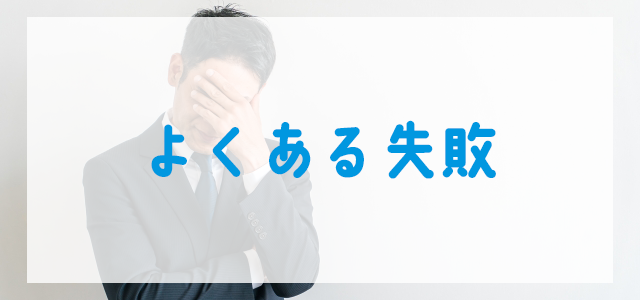
はじめに:安さの裏にあった“法的リスク”
「とにかく安くホームページを作りたい」
そんな思いで格安業者に依頼した結果、思わぬ“著作権トラブル”に巻き込まれたという企業が増えています。
画像の無断使用、文章の流用、素材ライセンスの不備……
気づいた時には法的責任を問われたり、損害賠償を請求されたりするケースも。
この記事では、実際のトラブル事例とともに、なぜ格安制作が著作権の危険を招きやすいのか、そしてその対策を詳しく解説します。
実録:格安業者に依頼して発生したトラブル
背景:5万円で作れるという甘い言葉
ある中小企業が、新規事業の立ち上げに合わせてホームページを作ろうとした時のこと。
「初期5万円、納期2週間」「テンプレートでスピード対応」とうたう業者に依頼。
やり取りはメールのみ、簡単なヒアリングと画像・テキストの送付で、サイトは完成したように見えました。
問題発覚:掲載画像に「著作権侵害」の警告
公開から約1ヶ月後、画像の権利者から「無断使用に対する削除と損害賠償の請求」が届いたのです。
調べてみると、使用されていた写真は有料素材サイトからの無断転載で、業者側が「フリー素材」と誤認して掲載していたものでした。
業者は「責任を負わない」と主張
契約書を見ると、小さく「著作権等の責任は発注者が負うものとする」と明記されていました。
結果、交渉・削除対応・賠償金支払いまで、すべて自社負担となったのです。
なぜ格安制作は著作権リスクが高いのか?
① 素材の使用ルールが曖昧・未確認
「ネットにある画像は使っていい」と勘違いしている制作者も少なくありません。
特に格安業者や副業系の個人制作者には、画像・イラスト・文章の著作権に対する理解が乏しいことがあります。
② 制作プロセスがブラックボックス化
安価でスピード重視の制作では、どの画像をどこから取得したのか、誰が書いたテキストなのかが確認できないことが多いのです。
③ 契約書が存在しない/内容が不十分
「口約束だけで進めた」「契約書をもらっていない」「テンプレ契約書で詳細が曖昧」──
このような場合、責任の所在が不明確になり、結局発注者側にすべてのリスクがのしかかることになります。
著作権侵害がもたらす“本当の代償”
① 損害賠償・削除請求のリスク
写真1枚で数万〜十数万円、文章の流用でそれ以上の金額を請求されることも。
損害賠償だけでなく、謝罪文や再発防止の誓約書提出を求められることもあります。
② 信用の低下とブランド毀損
「無断使用の企業」としてSNSで拡散され、炎上・謝罪・取引停止といった二次被害に発展するケースも。
BtoB企業では、取引先が離れる原因にもなります。
③ 修正費用と時間的ロス
該当ページの削除、写真の差し替え、法律相談、再構築──
安く作ったはずが、結果的に倍以上の出費と労力が発生することになります。
回避するために確認すべきポイント
① 使用素材の出典とライセンス確認
画像・イラスト・フォント・音源など、すべての素材について「出所」と「使用条件」を確認しましょう。
制作側任せにせず、リスト化してもらうのが理想です。
② 著作権条項を含んだ契約書を交わす
「誰が著作権を持つのか」「トラブル時の責任はどこにあるか」
これらが明記されていない契約書は、万一の際に自社がすべてを被る危険があります。
③ 制作過程の「透明性」を確認する
業者選定時には、制作フロー・使用ツール・納品物の権利帰属など、“何がどう作られているか”を把握することが重要です。
プロに依頼する際の「安全なチェック項目」
・素材ライセンスは明示されているか?
契約前に「使用する画像はどこから取得する予定ですか?」と尋ねてみましょう。
明確に答えられない場合は要注意です。
・制作物の著作権帰属はどちらか?
納品物が完全譲渡なのか、ライセンス契約なのか、所有権の範囲を明確にしておかないと後々トラブルになります。
・制作会社の過去トラブルや評判を調べる
GoogleレビューやSNS、口コミサイトで「著作権」や「無断使用」などのワードを検索してみましょう。
過去に類似トラブルがある会社は避けるのが賢明です。
まとめ:「安く済ませたつもり」が高くつく前に
格安制作は魅力的に見えますが、その背後には“見えないコスト=法的リスク”が潜んでいます。
ホームページは“公開したら終わり”ではなく、“ずっと公開され続ける”もの。
だからこそ、たった1枚の画像、たった1行の文章でも、著作権トラブルは後から企業の信用を大きく損なう要因になります。
価格だけでなく、「何に責任を持ってくれるのか」という視点で制作パートナーを選ぶことが、トラブル回避への最短ルートです。
