安く頼んだら地獄だった!ホームページ制作の落とし穴
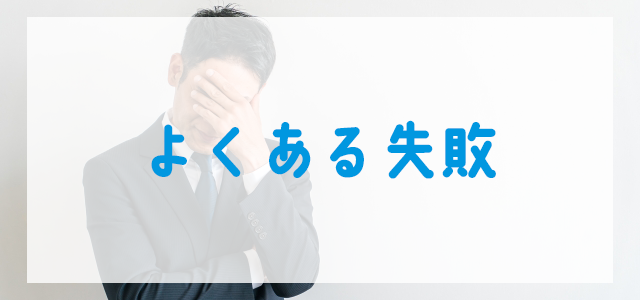
はじめに
「ホームページ制作は安く済ませるべき」という考え方は、多くの中小企業や個人事業主に根強く残っています。しかし“安さ”を最優先して外注すると、思わぬ落とし穴にハマることも少なくありません。
この記事では、実際に起きた失敗事例を交えながら、安価なWeb制作に潜むリスクと、失敗を避けるためのチェックポイントを解説します。
例:A社(地方の建設業)がフリーランスに依頼した結果、スマホ未対応のまま納品。問い合わせが激減し、全体の作り直しに至りました。
よくある“安かろう悪かろう”の実例
見積もり3万円、でも最終的に15万円?
「5万円以内でホームページを作成します!」という格安業者の広告に惹かれて依頼した企業の中には、後からの追加料金で総額が大幅に膨らんだというケースが少なくありません。
例:B社(人材サービス業)はSNS広告経由で格安業者に依頼。初期見積もり3万円だったが、スマホ対応・問い合わせフォーム・SSL対応などがすべて別料金で、結果15万円超に。
副業デザイナーの片手間制作
副業制作者や知人に頼んだ場合、「納期遅れ」や「修正対応の遅延」が頻発します。ビジネスにおける信頼とスピード感が失われることも。
例:C社(飲食業)は知人の副業制作者に依頼したが、修正に毎回1~2週間かかり、開店時期にサイトが間に合わなかった。
“安い”の裏に潜む構造的なリスク
コストを削る=ヒアリングも削る
費用を抑えるために、ユーザー分析や競合調査などの設計工程が省略されがちです。
「なぜそのレイアウトなのか」「誰に何を伝えるのか」といった基本が不明確なまま進行します。
例:D社(製造業)は契約書もなしに進行。画像をネットからコピーして使われ、著作権トラブルに発展し、別途で法的対応費用が発生。
テンプレートの使い回し
格安制作では、1つのテンプレートを複数企業に流用している場合が多く、他社とそっくりのデザインになることも。ブランディングが台無しです。
運用不在の納品主義
納品後のサポートがなければ、「どう更新するか」「誰が管理するか」が未解決のままになります。
自社で何もできず、問い合わせもできず、放置されるケースも多数。
失敗しないために確認すべきポイント
信頼できるパートナーかどうか
事前の打ち合わせで「競合は?」「目的は?」「成果指標は?」といった質問があるかを確認しましょう。
安いだけの業者は、聞かれる前提で動いていません。
例:E社(士業事務所)は安価テンプレ会社に発注。完成後の修正が都度2万円で、社内更新も不可能。結局使いものにならず。
契約内容の明示
「見積書」「契約書」「納品仕様書」の3点セットがあるかは要確認。特に「どこまでが料金内か」はトラブル回避の生命線です。
“安く済ませたつもり”が高くつく構図
やり直しコストが倍に
安く作ったサイトが結局役に立たず、再制作でさらに高額の費用が発生することもあります。
例:F社(教育関連)は大手風格安業者に依頼したが成果ゼロ。半年後に別会社に依頼し、1ヶ月で月5件のCVを獲得。
見られない=信頼されない
ユーザーからすれば、サイトが時代遅れ・スマホで見づらい・文字が小さいだけで、「この会社、大丈夫かな?」と不安に思われます。
良質なパートナーを選ぶには?
“作って終わり”ではなく“育てる前提”か
納品後もアクセス解析やUI改善の相談ができるパートナーであれば、費用対効果は圧倒的に高まります。
成果にこだわる姿勢があるか
「何件の問い合わせを目指すか?」「どの導線に誘導するか?」といった話ができるかどうか。
表面の“デザイン”だけで判断しないようにしましょう。
例:G社(小売EC)は格安にこだわり放置された後、適正価格の業者に依頼し直し。1ヶ月でCVが1.4倍に改善。
まとめ:安さに飛びつく前に考えたいこと
ホームページは「作ること」がゴールではなく、ビジネス成果を生む“営業資産”です。
だからこそ、「安い」ではなく「価値がある」ものを選ぶべきです。
価格だけを見て判断すると、“地獄”と呼べるような時間・コスト・信頼損失を招くことになります。
本当に必要なのは、“安さ”ではなく“目的を達成できる体制と伴走力”です。
