激安業者に依頼して消えたWeb担当の嘆き
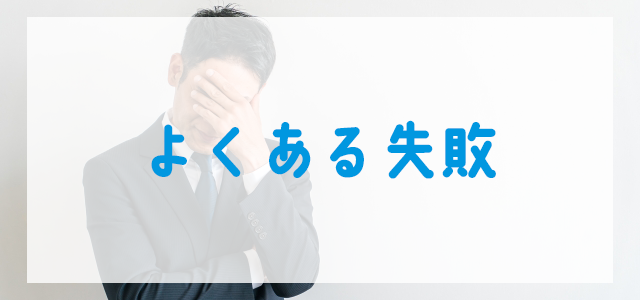
はじめに:「とにかく安く」が引き起こす落とし穴
「なるべく安くWebサイトを作りたい」──その気持ちはよく分かります。
しかし、安さだけで業者を選んだ結果、大きな後悔を抱えるケースが後を絶ちません。
特に中小企業やスタートアップのWeb担当者が、「激安制作会社」に丸投げしてプロジェクトが迷走する…そんな事例が多く存在します。
本記事では、実際に起きたトラブル例と、その根本原因、今後選定すべきポイントを具体的に解説します。
実録:消えたWeb担当が直面した“5つの地獄”
1. 担当者が突然音信不通
最も多いのがこれです。
「修正依頼をしたら返信が来ない」「電話も繋がらない」「納期が過ぎても連絡なし」──
激安業者の多くは、フリーランスや少人数で運営しており、急な事情で業務が止まるリスクがあります。
2. 提案力ゼロ、ただ言われた通りに作るだけ
「デザインがダサい」「構成が素人っぽい」──
そう感じても、向こうからは何のフィードバックもなく、改善提案もゼロ。
「プロに頼んだ意味がなかった」と感じる依頼主が多くいます。
3. 完成したサイトにエラーが多数
納品されたサイトをよく見たら、リンク切れ、スマホでの表示崩れ、文字化け…
動作確認すらまともにされていない粗悪品が納品されることも珍しくありません。
4. 納品後の修正がすべて「追加料金」
契約時には「軽微な修正は無料」と言っていたのに、実際には「ここは別料金です」と言われる始末。
安さで釣って、後から課金するビジネスモデルであることも多いのです。
5. 管理情報が共有されず、サイトの引き継ぎが不可能
ドメインやサーバーの情報、WordPressのログイン情報など、重要な管理権限を業者が握ったまま。
いざトラブルが起きても、誰も修正できない…という最悪の事態に。
なぜ「激安業者」はこうしたトラブルを生むのか?
1. 価格競争だけを武器にしている
「とにかく安く作ります!」という業者は、品質やサポート体制を削って価格を成立させているのが実態です。
2. サイト構築の全体設計がされていない
構成・導線・CV設計などは無視され、「とりあえず形にする」ことだけが目的になっている場合が多く、
成果が出ないサイトになりやすいのです。
3. 保守・更新・運用の視点がない
作って終わり、納品したら終了。
その後の運用や改善は想定していないため、担当者が困っても頼れない構造です。
4. 担当者が複数案件を抱えてパンクしている
「一人で10案件を抱えている」というような状況も珍しくありません。
結果として、対応が遅れる・雑になる・消えるという事態を招きます。
失敗しないために見るべき7つのチェックポイント
1. 過去実績とURLの公開状況
実績を「画像だけでなく実際のURL」で提示してくれるかを確認しましょう。
架空の制作実績や消えているサイトは要注意です。
2. 契約書に「納品範囲」「修正範囲」の明記があるか
曖昧な契約は、トラブルの温床になります。
修正回数・更新費用・納期などを必ず事前に文書で確認しましょう。
3. 管理情報の共有の有無
契約時に、ドメイン/サーバー/CMSログイン情報を渡す前提かどうかを明確にすべきです。
4. サポート体制と連絡手段の明示
「緊急時はどう連絡をとるか」「どのくらいの期間、修正対応してくれるか」など、“その後”の支援体制が明示されているかも重要です。
5. 制作意図や設計について質問した際の回答
「なぜその構成にしたのか?」と聞いて、きちんとした設計意図が語られるかは判断材料になります。
6. デザインとコーディングが別会社でないか
格安業者では「外注の外注」になっていることもあり、責任の所在が不明確になる原因です。
7. 口コミや第三者の評価
SNSやクラウドソーシングの評価欄、Googleレビューなど、第三者の意見を事前にチェックしておくのが無難です。
中長期的に見て「安かった」のか?
1. 機会損失という“見えない損害”
安く作れたとしても、デザインや構成が悪くてCVが出なければ「収益ゼロ」です。
実質的には大きな損をしている可能性があります。
2. 再制作のコストが二重でかかる
結局「使えないから作り直し」となると、時間もコストも二重にかかるという無駄な投資になります。
3. 社内の信頼・信用を失う
担当者として「安さで選んだ結果失敗した」となると、社内評価の低下や信頼の喪失につながりかねません。
まとめ:「安い」ではなく「適正な投資」を
ホームページは、企業にとっての「顔」であり、「営業の入り口」です。
だからこそ、目先の金額よりも、その先の成果やサポート体制を重視するべきです。
「安くてラッキー」ではなく「安くて危険だった」では本末転倒。
自社の信頼や集客の要となるサイトづくりだからこそ、“価格以外の判断基準”を持つことが、今後の成否を分けるカギになります。
