制作費が安くても修正で高くついた理由
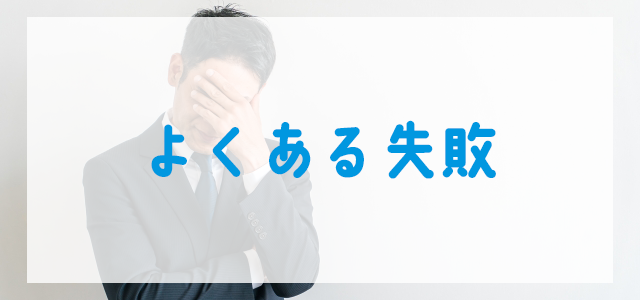
はじめに:「安さ重視」が結果的に高くついた話
「制作会社に頼むと高いから、なるべく安く仕上げたい」
そんな思いから、格安の制作業者や個人にホームページを発注するケースは少なくありません。
しかし、納品後に気づくのは、“思った通りにできていない”という現実。
その結果、修正や追加対応を重ねることで、最終的には想定以上の費用と時間がかかることも珍しくありません。
この記事では、なぜ「安く作ったのに高くついたのか?」その理由と防止策について詳しく解説します。
よくあるパターン:「基本料金は安い」が落とし穴
初期費用に含まれていない項目が多すぎる
「5万円でホームページ制作」といった格安プランには、ページ数制限・スマホ対応なし・画像用意は別途といった制限があることがほとんどです。
依頼者はそれを知らずに発注し、あとから「この対応はオプションです」と追加費用を請求されるケースが頻発しています。
修正1回ごとに追加料金が発生
「修正3回まで無料、それ以降は1回5,000円」といった料金体系も要注意。
やり取りのたびに料金がかさみ、最終的には数万円〜十数万円の修正費がかかることもあります。
コミュニケーションが不十分で手戻りが多発
安価な制作では、ヒアリングの時間が限られており、仕様のすり合わせが不十分になりがちです。
結果として「思っていたのと違う」となり、何度も修正を依頼するハメになります。
実例で見る「安く発注したのに高くついた」ケース
事例1:テンプレート制作で修正が効かず再構築
G社は、テンプレート使用による格安制作(8万円)を選択。
しかし納品後、デザインや導線が業種と合っておらず、細かい修正がすべて「できない」または「別料金」と言われ、結果的に別業者に20万円で再構築を依頼することに。
事例2:写真やテキストの差し替えに高額請求
H社は、制作後のちょっとした画像変更や文言修正に1回5,000円の費用を提示され、最終的に月2〜3万円の追加請求が発生。
「安く作っても更新できないなら意味がない」と感じ、CMS付きの別プランに移行。
事例3:ページ追加対応が“ほぼ新規制作扱い”
I社では当初「5ページ構成」で制作依頼。
しかし、サービス追加に伴ってページを1つ増やしたいと相談したところ、“構成全体を見直す必要がある”との理由で6万円の見積が提示された。
結果的に、自作していた方が早くて安かったという皮肉な展開に。
なぜ修正費用で予算オーバーになるのか?
発注者と制作者の“完成イメージ”がズレている
言葉だけのやり取りでは、完成イメージの共有は困難です。
そのズレが、「ここはこうしてほしかった」という“やり直し”を生む最大の原因になります。
契約書や仕様書がない/曖昧
修正の定義や、対応回数・条件が契約に明記されていないと、制作者と依頼者の解釈が異なり、揉める原因になります。
制作の知識がないと、何が“有料修正”か判断できない
Web制作に不慣れな発注者にとって、「これは当然含まれていると思った」が通じないことも。
専門用語や構成仕様の知識がないと、請求内容の妥当性も判断できません。
最終的に“高くつく格安案件”の特徴
修正回数や対応範囲が曖昧
「軽微な修正は無料」「ある程度までなら対応可能」など、あいまいな条件表現は避けるべきです。
見積書や契約書で「明文化」されていないものは、後からトラブルの元になります。
CMS(更新機能)がない/使えない
納品されたサイトがHTML直編集のものだった場合、更新のたびに外注が必要になります。
結果的に、修正のたびに数千円〜数万円がかかる構造になります。
修正対応のスピードが遅い
格安業者は他の案件と並行して進めていることが多く、「すぐ直してもらえない」「返事がこない」といった問題も発生しがちです。
最初に確認すべき「修正」に関する4つの項目
1. 修正対応の範囲と回数
「どの範囲までなら無料か」「何回まで対応可能か」を必ず確認し、契約書または見積書に記載しておきましょう。
2. 納品物の形式と更新方法
CMS(WordPressなど)で管理画面から自分で更新できるのか、制作会社に都度依頼が必要なのかを事前に確認しましょう。
3. 今後の運用に必要な対応料金
定期的な修正・バナー変更・メニュー追加など、実際に発生しそうなケースの費用感を事前に質問するのがベストです。
4. 修正対応のスピード
「どれくらいで反映されるか?」「営業日換算か?」といった点も、実務に直結する大事な項目です。
まとめ:安さだけを基準に選ばないために
制作費が安いことは、一見メリットのように感じられます。
しかし、完成後に修正が多発し、結果的に高くついたという事例は少なくありません。
本当に見るべきポイントは「初期費用」ではなく、以下の3つです:
- 修正対応の範囲と費用が明確か
- 将来的に自社で更新できる仕組みか
- 完成後の伴走体制があるか
「安く作ったはずが、逆に高くついた」
そんな事態を避けるために、契約前に“修正の仕組み”まできちんと確認しましょう。
安さは「価値」ではなく「条件」です。その裏にあるコスト構造を見極める目こそが、発注者に求められています。
