初期費用が安くても後から追加料金が多数発生
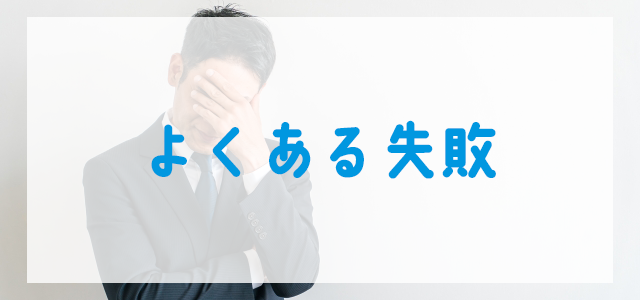
はじめに:「安く済むはずが高くついた…」
「初期費用3万円でホームページ制作します!」そんな広告に惹かれて依頼したものの、最終的には20万、30万円以上に膨れ上がっていた…というケースは少なくありません。
本記事では、格安をうたうWeb制作で発生しがちな「追加料金トラブル」の実態と、その予防策について詳しく解説します。
よくある「安価に見せかけた請求」の手口
① ページはトップのみ、他は別料金
「ホームページ制作」と言いつつ、実際にはトップページ1枚しか含まれていないプランも存在します。
会社概要、サービス紹介、アクセスページなどはすべてオプション扱いで、1ページごとに数万円の追加費用が発生することもあります。
② お問い合わせフォームが別途請求
「フォーム設置は含まれて当然」と思っていても、「動作保証はしません」「別料金です」と言われるケースがあります。
フォーム一式に3万円〜5万円、さらにメール設定やサーバー設定で別費用がかかることも。
③ 納品後に保守契約を強制
「月額保守がないと不具合対応しません」と言われ、急きょ月額1〜2万円の保守プランを契約する羽目になる企業も。
最初から明示されていない費用は、トラブルの元になります。
「安い業者」の見積書にありがちな特徴
① 「一式」という記載の多用
「デザイン一式」「構築一式」など、内容が不明確なまま一括表示されている場合、何が含まれていて、何が追加なのかが分からないという状況に陥ります。
② 工数に関する記載がない
作業内容のボリュームがわからないまま契約すると、修正のたびに「想定外」とされ、追加費用を請求されやすくなります。
③ 修正回数に上限あり
格安プランには、「2回まで無料、3回目以降は有料」といった制限が付いていることも多く、納得いくまで修正できない事態も起こりがちです。
実際の被害事例
ケース①:「3万円で作ります」に飛びついた結果…
中小企業が「初期費用3万円」の広告に惹かれて依頼。
ところが、ロゴ設置、Googleマップ、スマホ対応、フォーム機能…すべてがオプション扱い。
納品時の合計額は28万円にまで膨れ上がっていたという実例があります。
ケース②:追加ページ1枚あたり3万円
最初に示されたプランは「トップページ1枚のみ」だったにも関わらず、それを知らずに依頼。
会社概要や採用情報を追加したところ、1ページ3万円、合計6ページで18万円の請求に。
「最初に言ってくれれば…」という後悔の声も。
なぜ「後出し請求」が生まれるのか?
① ユーザー側の確認不足
業者の説明不足もありますが、「まさかこれが含まれていないとは…」という認識のズレが原因の一つです。
質問せずに「お任せ」にした結果、希望機能がすべてオプションになってしまうケースもあります。
② 安さを入口に契約を迫るビジネスモデル
低価格をうたうことでとにかく問い合わせを獲得し、契約後に利益を回収する構造の業者も存在します。
③ 契約書や見積書の詳細が不十分
契約段階で仕様や費用の範囲を明記していないと、「これは別です」といくらでも後付けされるリスクが高まります。
トラブルを避けるための5つの対策
① 必ず「作業範囲一覧」をもらう
トップページだけか?スマホ対応は?
必要な項目が明記された仕様書や見積書をもらいましょう。
② ページ数と構成内容を確認する
「何ページあるのか」「その中に含まれる要素は何か」まで、具体的に確認することで追加料金の芽を潰せます。
③ フォーム・SNS・SEOなどの有無を聞く
「当たり前」と思われる要素が入っていないことも。
自社が必要な機能が初期費用に含まれているかをチェックしましょう。
④ 保守・更新の対応範囲を明確にする
納品後のサポートが有償か無償か、修正は都度見積か、回数制限があるかなどを契約前に明らかにします。
⑤ 口頭説明は必ず「書面」で残す
「これは大丈夫です」という言葉も、メールや契約書で文書化しておくことが重要です。
まとめ:「安い」は本当に得なのか?
格安のWeb制作には、あとから追加料金が発生する仕組みがあることが少なくありません。
安さに惹かれて契約した結果、「オプション地獄」に陥って後悔する企業も多いのが実情です。
見積・契約段階で「本当に必要な機能がすべて含まれているか?」を細かく確認し、信頼できる業者を選ぶことが、費用トラブルを避ける最大の防御策になります。
