フォントや色使いがチグハグで信用されない
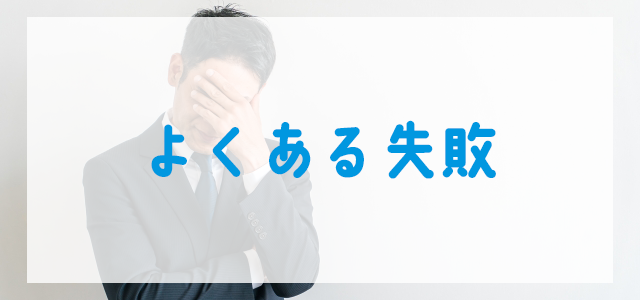
はじめに:「なんか信用できない」の正体
「ちゃんとサービス内容は書いてあるのに、問い合わせが来ない」
「ページを見てもらえているはずなのに、離脱率が高い」
そんな時に疑ってほしいのが、“フォントや色使いのちぐはぐさ”です。
ユーザーの多くは、数秒でWebサイトの第一印象を判断しています。
つまりデザインの違和感=「信用できなさ」と直結するのです。
この記事では、なぜデザインの統一感が信頼につながるのか、チグハグなデザインがどのようにマイナス印象を生んでしまうのかを、具体的な事例とともに解説します。
なぜ“デザインのチグハグさ”が信用を下げるのか
① フォントの不統一が「雑さ」に見える
本文が明朝体、見出しがゴシック体、ボタンが手書き風──
それぞれのフォントに個性があるのは事実ですが、意図のないバラバラな使い方は「ルールのなさ=いい加減さ」と捉えられてしまいます。
② 色のちぐはぐさが「不安感」を与える
ピンクの背景に黄色の文字、急に真っ黒のブロック、ボタンが緑だったり赤だったり。
統一感のない配色は、ユーザーに「どこを見ていいか分からない」「読みづらい」「信用できない」という印象を与えます。
③「公式感」がなくなる
特に企業や士業サイトの場合、公的な印象・堅実さ・安心感が求められるもの。
フォントがポップ体だったり、色がパステル系に偏りすぎていたりすると、「本当に大丈夫な会社?」と疑念を持たれるリスクがあります。
チグハグデザインで起きる5つの“信用損失”
① サービスの質も低く見える
サイトのデザイン=企業の印象です。
「このページが雑なら、サービスも雑なのでは?」と連想されるのは避けられません。
② 読みにくく、内容が頭に入ってこない
フォントのサイズがバラバラ、色が薄くて見えない、行間が詰まりすぎ。
こうした“見にくさ”がユーザー体験を下げ、結果的に離脱を招きます。
③ スマホでの表示がさらに悲惨に
PCで整っていても、スマホで見ると全体が崩れたり、色のバランスが狂ったりすることも。
レスポンシブ設計でのデザインの統一性も重要な信頼指標です。
④ 競合と比較された時に負ける
同業他社のWebサイトが整っている場合、「こっちはしっかりしてそう」「あっちはちょっと不安」と判断されるのは自然なことです。
⑤ 広告やSNS導線も効果が出にくい
「広告を見てクリックしたけど、飛んだ先のページが雑だった」
その瞬間にユーザーは離脱し、二度と戻ってこない可能性が高まります。
ありがちな“デザインミス”とその回避策
① フォントが3種類以上使われている
ベースは1種類、アクセントでも2種類までが理想。
Webフォントを気軽に使える時代だからこそ、「厳選する」姿勢が必要です。
② ボタンや見出しの色に統一性がない
ページ内で使う色は原則3色まで。
ブランドカラー+補助色+強調色で構成すると視認性とデザイン性を両立できます。
③ セクションごとの背景色が毎回違う
区切りを見せるための配色は重要ですが、色味の方向性(明るい/暗い、寒色/暖色)をブレさせないのが基本です。
④ テキストカラーのコントラストが低い
グレー背景に薄いグレー文字、写真の上に白文字など、読みづらい構成は「読ませたくないのか」と誤解されることすらあります。
信頼されるWebデザインの“5原則”
① 一貫性
見出しのフォントサイズ、本文の行間、ボタンのデザイン。
これらがページ全体で“規則に従って設計されている”ことが、ユーザーに安心感を与えます。
② 意図のある余白
ギチギチに詰まったコンテンツは「古臭さ」を感じさせます。
情報量ではなく“読みやすさ”を優先したレイアウトが信頼されます。
③ ブランドカラーの活用
コーポレートカラーがあるなら、それを軸にデザインを構築。
無理にオシャレ感を狙わず、色で“らしさ”を伝えるのがプロの技術です。
④ 視線誘導の設計
ファーストビューで目に入る文字、スクロール先の見出し、ボタン配置など、ユーザーの動線を考えたデザインこそがコンバージョンにつながります。
⑤ “無駄に凝らない”シンプルさ
色を増やせばよい、フォントを変えればよい、装飾すればよい――
それは間違いです。大事なのは「伝わるかどうか」。その視点で、あえて引き算を選ぶ勇気も重要です。
まとめ:「なんか信用できない」を回避する第一歩
デザインは“感覚”ではなく“戦略”です。
ユーザーはわずか数秒であなたのWebサイトを評価し、信頼するかどうかを判断します。
そのときにフォントや色使いがちぐはぐであるだけで、すべての情報の説得力が失われてしまうのです。
プロに頼むことで、ただ“きれい”なだけでなく、“信頼される構造”を得ることができます。
安易な自己流ではなく、明確なデザイン方針と統一性をもって、「伝わるサイト」をつくりましょう。
