個人に頼んだが連絡が取れなくなった話
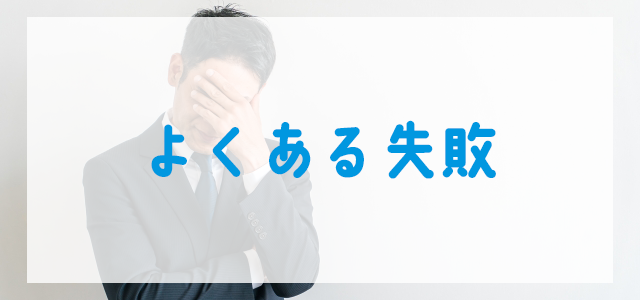
はじめに:「個人に頼んだら消えた」よくある話
ホームページやLP、ECサイトなどを「コストを抑えて作りたい」と考える企業や個人事業主にとって、個人フリーランスへの依頼は非常に魅力的に映ります。
「知人の紹介だから安心」「ポートフォリオが綺麗だったから信頼できそう」
そう思って依頼した結果、途中で連絡が取れなくなるという事態に直面するケースは、実は少なくありません。
この記事では、実際の事例をもとに、個人への外注で起こりやすい「連絡断絶」の背景と、未然に防ぐための対策を解説します。
事例1:知人経由で紹介されたデザイナーが音信不通に
「紹介だから大丈夫」の油断
A社は、知人から「フリーで優秀なデザイナーがいる」と紹介を受け、簡単な打ち合わせを経てLP制作を依頼。
「最短2週間で納品可能」という言葉を信じ、正式な契約書を交わさず、半金を前払いしたそうです。
しかし、1週間後に修正指示を送ったところから、連絡が一切返ってこなくなったとのこと。
何が問題だったのか?
紹介者も「最近忙しいらしい」としか言わず、制作状況は完全にブラックボックス。
依頼したA社は、スケジュールが大幅にズレ込んだだけでなく、代替手配にも時間がかかり、広告出稿のタイミングを逃すことになりました。
事例2:SNS経由で依頼した個人クリエイターが突然音信不通
安さと作風に惹かれて即依頼
Bさん(個人事業主)は、X(旧Twitter)で活動していたフリーのWeb制作者に連絡し、LP制作を依頼。
「対応早いです!」「特急OK!」という文言に惹かれ、DMだけでやり取りを進めてしまいました。
途中まで順調だったが…
ワイヤーまでの作業は順調でしたが、その後デザイン提出予定日になっても納品なし。
数日後、「体調不良で遅れます」という連絡を最後に、SNSアカウントごと消失。
Bさんは、着手金3万円を支払ったまま、制作も納品も失うことになりました。
事例3:クラウドソーシングで即決→制作途中で失踪
評価が高い=信頼できると思い込んだ
C社は、クラウドソーシングで評価4.9・実績多数という個人クリエイターに依頼。
対応も丁寧で、仮納品までは順調。しかし修正を依頼したところ、1週間以上返信がなく、その後も連絡が途絶えがちに。
やがて連絡不能に
案件の途中で「急な家庭の事情」とだけ連絡があり、それ以降は完全な沈黙。
C社は、中途半端なサイトと進捗資料だけを残されて、別の業者への再依頼を余儀なくされました。
なぜ“個人依頼”では音信不通が起きやすいのか?
契約書・仕様書がないまま進行しがち
多くのケースでは、メールやチャットのみで口約束のまま作業が進行しています。
そのため、トラブルが起きたときに責任の所在が曖昧になりやすいのです。
個人の業務体制は不安定
体調不良や家庭の事情、急な引っ越しなど、個人の生活が業務に直結するため、継続的な対応が困難になることもあります。
報酬が低すぎると“後回し”にされる
「安く引き受けてもらった」案件ほど、他の高単価案件が入ると優先順位が下がり、放置される傾向があります。
音信不通のリスクを減らすためにできること
契約書と納期・条件の明文化
どんなに信頼できる人でも、納期・報酬・納品範囲を契約書で明確化することは必須です。
支払いスケジュールや遅延時の対応についても記載しましょう。
ポートフォリオだけでなく「制作体制」も確認
過去の実績が素晴らしくても、複数案件を抱えている・納期遅延歴があるなど、背景を確認することが重要です。
連絡手段を複数確保する
メール・電話・チャット・SNSなど、複数の連絡手段を確保しておくことで、突然の音信不通リスクを下げられます。
万が一、連絡が取れなくなったら?
まずは記録を整理しておく
やり取りのログや支払い履歴、提出された資料をすべて保存・整理しておきましょう。
後の交渉や法的対応の材料になります。
プラットフォーム経由なら運営に相談
クラウドソーシングなどを利用していた場合は、運営事務局に早めに相談することで、支払い保留や対応催促が可能です。
法的措置の可能性も検討
明らかな契約違反や詐欺性がある場合、少額訴訟や内容証明による催促も視野に入れましょう。
ただし、費用対効果や手間をよく検討する必要があります。
まとめ:「安くて気軽」な個人依頼に潜むリスク
個人クリエイターへの依頼は、コスト面で魅力的であり、柔軟でスピーディーな対応が期待できる反面、連絡断絶・納期遅延・品質トラブルといったリスクが伴います。
以下の3点を徹底することで、トラブルを大幅に減らせます:
- 契約書・仕様書の作成
- 業務体制と対応履歴の確認
- 連絡手段・責任体制の確保
「まさか、あの人が…」という思い込みが、もっとも危険です。
安易な依頼の前に、“もし途中で連絡が途絶えたら?”という視点を持ち、対策を講じておくことが、最終的には時間とコストを守る鍵になります。
