知人の紹介=安心ではなかった件
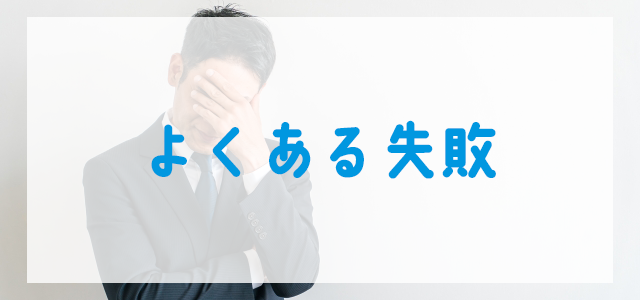
はじめに:信頼できるはずの「知人の紹介」で失敗?
ホームページ制作を依頼する際、「知人からの紹介だから安心」という理由で業者や個人に依頼する方は少なくありません。
しかし、それが思わぬトラブルや後悔に繋がることもあります。
本記事では、知人の紹介でホームページ制作を依頼したものの、後に「紹介=安心ではなかった」と感じた実例や、注意点、今後の対策について詳しく解説していきます。
なぜ「知人の紹介」で頼むのか?
紹介という“信頼フィルター”の存在
人は情報の出所が明確であればあるほど安心感を覚えます。特に、信頼している知人からの紹介であれば、「それなら大丈夫だろう」と判断しがちです。
これはいわば「信頼のバイパス」。本来なら時間をかけて確認すべき実績やスキルを、紹介者への信頼によって省略してしまう心理が働きます。
コスト・コミュニケーション面でのメリット
「融通が利く」「安くしてくれるかも」「スピードが早そう」など、紹介だからこそ期待する要素も多くあります。
とくに制作費が抑えられそうという点に魅力を感じて、紹介経由で発注を決めるケースは非常に多いです。
実際にあったトラブル事例
事例1:納品が遅れ続けたフリーランス
知人の紹介でフリーランスの制作者に依頼。「忙しいらしく少し遅れる」と言われていたが、気がつけば納期は3か月以上遅延。
紹介者に相談しても「忙しい時期だから」としか返されず、結果的に制作が中断されたままフェードアウト。
事例2:専門知識が不足していた元デザイナー
昔の同僚が「知り合いにデザイン得意な人がいる」と紹介。確かにデザインは綺麗だが、SEOやスマホ対応、セキュリティ面などにまったく配慮されておらず、運用開始後に問題が頻発。
結局、専門業者に再度依頼し直す羽目に。
事例3:「仲が良いから」で進んだ口約束契約
知人を通じて若いエンジニアに発注。契約書も見積もり書もなく、「お互い信頼してやりましょう」でスタート。
途中で仕様変更をお願いしたところ、「それは別料金」と言われ、もめた末に作業が停止。
紹介者にも気を遣い、強く言えず、トラブルはこじれてしまいました。
紹介による依頼の「見落としポイント」
紹介者がその人のスキルを保証しているわけではない
紹介者は「人柄」を知っていても、「スキル」や「実務経験」を知らないケースが大半です。
そのため「感じの良い人だけど制作は素人に近い」ことも。実績やポートフォリオをきちんと確認することは、紹介であっても絶対に必要です。
契約や仕様書を省略しがちになる
紹介経由の発注では「契約書なし」「仕様書なし」「見積もり曖昧」といった曖昧な形で進めがちです。
しかし、いくら紹介でも、ビジネスはビジネス。条件や責任範囲を文書化しないと、後々の揉め事の原因になります。
紹介者に気を遣いすぎてトラブルを放置する
問題が起きても「紹介してもらった手前、言いづらい」となりがちです。
結果的に、本来なら途中で打ち切るべき案件がズルズル進むことも多く、時間とお金を浪費してしまうことになります。
どうすれば防げたか?事前のチェックポイント
紹介でも必ず「第三者」として接する
紹介されても、発注先とはあくまでビジネス関係。
情や義理よりも、スキル・実績・条件を冷静に見て判断する姿勢が必要です。
ポートフォリオと実績を必ず確認する
過去にどんなサイトを作ったのか、どのくらいの期間で納品しているのか、公開URLなどを提示してもらうことで、信頼性の判断材料になります。
仕様・契約・支払条件を明文化する
紹介者がどうであれ、発注条件・納品物・金額・支払い期日・修正対応の範囲は書面で残すべきです。
これがあるかどうかで、「言った・言わない」のリスクを大きく減らすことができます。
まとめ:紹介であっても“確認と契約”を怠らない
「知人の紹介=安心」という考え方には、大きな落とし穴があります。
むしろ、その安心感が冷静な判断を鈍らせ、トラブルに発展するリスクを高めてしまいます。
紹介であっても、以下の点を忘れないことが大切です:
- スキルと実績は自分で確認する
- 契約や見積もりは必ず書面で
- 感情ではなくビジネスとして接する
紹介者も悪気があるわけではありません。ただし、紹介者がすべてを保証してくれるわけでもありません。
大切なのは、自社の責任で最終判断を下すこと。その意識が、後悔のない制作を実現します。
