Googleしない若者はいない
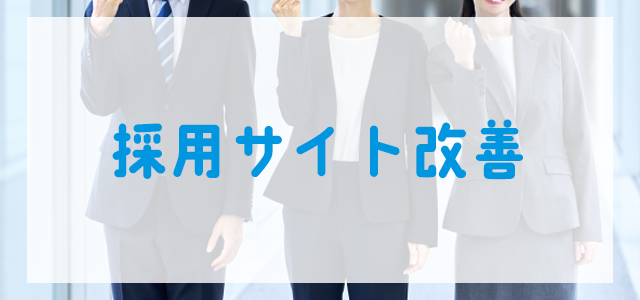
Googleしない若者はいない
「最近の若者はGoogleを使わない」などと言われることもありますが、それは誤解です。 Z世代・ミレニアル世代を含む求職者層の多くは、企業について調べる際、まずGoogleなどの検索エンジンで情報を集めます。公式サイト、口コミ、SNSなど、複数の情報源をチェックしながら「どの会社に応募するか」を決めているのです。
つまり、採用成功のカギは、検索行動にしっかりと対応したWeb対策にあります。本記事では、企業の採用ページが検索経由で見られるために必要な施策=「採用SEO」の考え方と実践方法を解説していきます。
なぜ今、検索エンジン対策(SEO)が採用に効くのか
求職者の行動はまず「検索」から始まる
求人広告やSNS投稿などで企業を知った求職者が、次に取る行動は「Google検索」です。たとえば「●●株式会社 評判」「●● 採用」などのキーワードで企業名を調べ、どんな会社なのか、働く環境はどうなのかを確認します。
ここで企業の採用ページがヒットしなければ、その時点で候補から外れる可能性もあります。つまり、検索結果に“出るかどうか”が応募数に直結する時代なのです。
「企業名+評判」「職種+エリア」などの実態検索ワード
求職者が実際に使っている検索キーワードは、「企業名+評判」「職種+地域」「業界+働き方」などが主流です。
こうした“自然な検索語”に対して、自社の採用情報がしっかりヒットするかが重要です。タイトル、見出し、URL、本文中のワード配置といったSEOの基本が求められます。
採用ページが見られない理由
コーポレートサイトの中に埋もれている
多くの企業が採用情報をコーポレートサイトに載せていますが、導線が弱くて見つけづらい構造になっていることが多くあります。リンクがフッターにあるだけ、スマホで探しにくい、といった問題が典型例です。
検索に引っかからない・タイトルが弱い
採用ページのタイトルが「採用情報|株式会社●●」では、「施工管理 採用 東京」などの検索にヒットしません。
検索エンジンには検索意図に沿った具体的な語句を含めたタイトル・見出しの設計が必要です。
求職者を“採用ページ”に導く導線設計
検索ワードに応じたLP設計とタイトル設計
1ページですべて紹介するのではなく、職種や条件別にLPを用意し、それぞれに対して具体的なタイトル設定を行うのが有効です。
職種・業務・エリア別などのセグメント化
求職者の「自分に関係ある情報があるか」を即座に伝えるために、職種別・エリア別にページを分け、各ページに社員の声や具体的業務内容を入れることが有効です。
Googleビジネスプロフィールと連携する
Googleマップに企業情報が出るようにし、そこから採用ページへのリンクを設置することでローカル検索にも対応できます。
採用SEOでやってはいけないこと
社名だけで上位表示を狙うのは逆効果
「株式会社●● 採用」だけに最適化しても、実際の検索では「職種×勤務地」などの複合ワードが使われます。
求人媒体任せで「自社での対策」を怠る
求人媒体に頼るだけではなく、自社サイト側でもSEOによる長期的な資産化を図るべきです。
キーワードの羅列や不自然な文章は逆効果
自然な日本語、読みやすさ、検索意図に沿った構成が評価されるため、無理な詰め込みは逆効果です。
中小企業でもできる採用SEOの実践ステップ
最低限押さえるべきタグ設計
タイトルタグに「職種・勤務地・特徴」を含めることが基本です。見出しタグ(h1〜h3)は構造の明確化とキーワード配置に活用しましょう。
ブログ・社員紹介・Q&Aの活用
「よくある質問」や「社員の声」はSEOにも求職者対応にも有効です。定期的に更新することで検索評価が上がります。
自社の“らしさ”を伝えるページ構成とは
中小企業こそ、社員間の関係性や職場の雰囲気など、他社と違う“リアル”を伝えることで、求職者の記憶に残ります。
まとめ:検索で選ばれる企業になるために
求職者にとってGoogle検索は、応募前の当たり前の行動です。 SNSや求人媒体で知った企業も、まず検索して評判を調べてから応募を判断します。
検索に出ない=存在しないと見なされる今、検索で見つけてもらうためのSEO対策は不可欠です。
特に中小企業は、採用LPや社員の声などを使って“検索されるページ”を育てることで、求人媒体に頼らない採用戦略を築けます。
最終的には、「この会社、なんかいいな」と思ってもらえるような“共感”を生むページ作りが大切です。 理念や働き方、社風など、企業の素顔を丁寧に見せることで、検索エンジンにも、求職者にも“選ばれる”ページになります。
